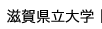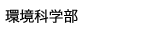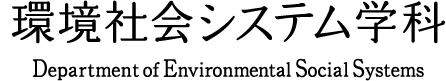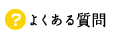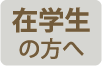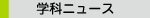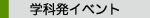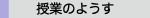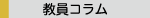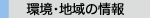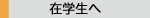社会におけるコモン・センスの学ー私の環境学ー 【秋山道雄】
2014年05月15日(木) 09:29更新
問題のゆらぎ
環境学の特徴は、問題解決を指向している点にある。ところが、一般的には問題がすでに自明なものとなっているとは限らない。公害問題のように、具体的な被害が発生し、因果系列の明らかな場合には、解決のための技術的な対策や制度的な対応の経路もはっきりしているケースが多い。
それにたいして、未来に被害の発生が予測されるケースや被害者が不特定とみられるケースでは、問題への関心が共有されるとはいいがたい。こうした場合には、問題の発掘とその解明にまず焦点をあわせることが必要となろう。さらに、人間の生命や生活への被害を防止するという次元をこえ、環境の質を向上させるという目的を設定した際には、価値判断の共有が課題となってくる。
社会のなかで、特定の問題や問題群に人々の関心があつまり、その解決にむけた行動がとられるまでには、まず対象を把握し、それにたいする態度を形成したのち、意思決定にいたるというプロセスがある。そこで、こうした過程の各段階で環境学が直面する問題を考えてみよう。
〔対象把握〕
1988年あたりから、にわかに地球環境問題へ関心があつまってきた。まず、国際政治の場でこれがとりあげられ、やがて一般の市民に広がっていった。1992年の地球サミットがひとつの頂点をなしたのは、まだ記憶にあたらしい。世界的に注目をあつめているとみられる地球環境問題であるが、この場合、各地の住民に問題は共有されているであろうか。今回は、国際政治の機微が問題の発端になったことは事実である。しかし、地球的問題への関心は早くから芽ばえていた。
たとえば1960年代には、K.ボールディングが宇宙船地球号の未来に警告を発し、問題が局地的なものではなく地球的なものであることを指摘していた。ローマクラブが1970年に発表した予測も、人々の関心を地球的問題にむけるのに貢献した。このころから、すくなくとも先進工業国においては、環境問題を地球規模でとらえるべきことが認識されていたといえる。
こうした認識の基礎には、20世紀の科学技術によって、われわれが宇宙からの視線を獲得したことが大きく作用している。人工衛星から地球をながめた宇宙飛行士が、「地球は青かった」というメッセージを伝えてきたのは、20世紀も後半に入ってからのことであった。人類の一員が地球以外の天体に着地し、地球の客観的な姿をとらえたのはそれから10年ほどのちのことである。そして、1972年から人工衛星をつうじて地球の写真が連続的に送られてくるようになった。宇宙からの視線による地球の監視は、あたらしい地球像の創出とむすびつく。つまり、地球像が操作の対象になるという段階を迎えたのである。これは、ある面で天動説から地動説への移行をうながしたコペルニクス的転換に匹敵する経験であった。
〔態度形成〕
宇宙からの視線をつうじた客観的な地球像の把握は、科学的な世界観にもとづいている。ところが、地球の現状にたいする認識は、個人や集団のあいだでかならずしも共有しうるとは限らない。個人のメンタルマップ(頭のなかの地図)に描かれた地球像は、同じ資料を共有している場合であっても、微妙に異なる。同じ時代に同一の地域で暮らしていても、価値観が異なればメンタルマップには差異がある。これが、時代や住む地域を異にしていると、そのずれははるかに大きい。個人や集団のもつ文化的背景が、メンタルマップの形成に大きくあずかっているのである。ここでは、共通の地球像をむすぶことはあまり期待できないであろう。
個人や集団のもつ美意識が文化的背景によって異なることはよく知られているが、自然の姿にたいする素朴な感動は、こうした文化的背景の差をこえた共通の感覚を生みだすことがある。
アメリカとカナダの国境にある五大湖は、宇宙からながめると、青く輝く宝石のようにみえるといわれている。これを、アメリカ・インディアンはギッチーグミー(太陽の照る大きい海)とよんでいた。人工衛星からみた地球の青さに感動した宇宙飛行士と五大湖を前にしたアメリカ・インディアンの感覚とは、以外に近いところにある。自然の景観が、人間の精神を深いところでゆさぶり、時間と空間の距離を縮めていく。こうした感動が、自然にむきあう態度に影響をあたえ、それが個人や集団の美意識に作用するのはあらためていうまでもない。素朴な感動や美意識をつうじた人間的な了解は、自然にたいする共通の感覚を培う可能性をもつのである。
〔意思決定〕
科学的な認識や美意識をつうじて、問題にむきあう態度を共有しうるようになったとしても、これがある選択にむすびつくまでには別の制約が横たわっている。地球的問題にそくしていうと、それは人口増加のパラドックスに典型的にみられる。
現在50数億人の人口は、21世紀のなかばに100億人に達するという予測がある。人口増加は、地球上での資源の枯渇や環境の制約という問題に大きく作用するとみられ、これへの対応が国際社会の大きい課題であるのは疑いない。ところが、日本をふくむ先進工業国では高齢化がすすみ、21世紀には人口増加が停止するのみならず減少にむかうと予測されている。こうした予測にもとづいて、むしろ人口の増加傾向をとりもどす方策が検討されるようになった。地球規模では人口増加をいかにとどめるかが大きい課題であるのに、先進工業国ではいかに人口の増加を図るかが課題となっているのである。先進工業国がその目指すところにすすんでいくならば、地球的課題と摩擦を起こすであろう。
さまざまな便益の享受と費用負担のずれは、これまでのところ主として局地的なものであったため、国民国家の枠内で対処されてきた。しかし現在、そのずれは地球規模で発生し、拡大しようとしている。そのため、こうしたずれを狭める方向で国際共通ルールを確立していくことが今日の課題であろう。共通の意思決定にいたるためには、ずれの発生と拡大という問題にたいする関心の共有が欠かせない。
共通感覚による架橋
20世紀の科学技術は、地球の住人にあたらしい地球像を提供した。人類は、それまでの歴史にはみられなかった経験を経ることによって、分水嶺をこえたのである。だが、この成果は地球上の住人に等しく共有されているわけではない。人間が特定の政治や経済や文化のもとで生活していることから、こうした偏在は発生する。地球的問題とむきあうとき、この事実を確認しておくことは重要であろう。語られている問題が一見自明で、その解決策もみえていると思われるものでも、個人がたっている位置と問題とのあいだには相当の距離があると実感される場合がある。それを埋めていくのが、人々の共通感覚であろう。
20世紀における科学技術の発展は、人間を遠いところへつれてきはしたが、一方でその地球を攪乱するのにも大きくあずかっていた。環境学は、派生した問題の発掘や解明とならんで、これを克服する筋道をつけるという課題に直面している。そのため、人々の選択行為に先立つ、対象把握・態度形成・意思決定という一連の過程に光をあて、共通感覚を培うための可能性を探っていくことは、発展途上の環境学にとってその柱となるものであろう。
(『環境科学部 年報 第1号』 1997年3月31日)