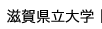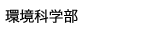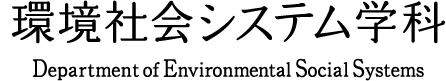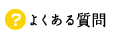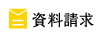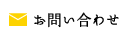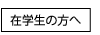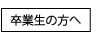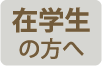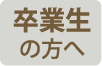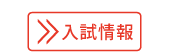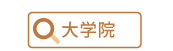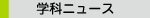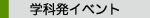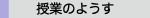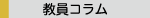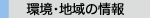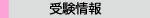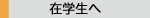研究と実践の両面から取り組む 脱炭素地域づくり中間支援組織の活性化 【平岡俊一】
2025年04月28日(月) 01:43更新
大学教員の中には、学内での教育や研究だけにとどまらず、実社会で様々な実践的な取り組みに関与している人も少なくありません。私自身も、もともと環境NPO/NGOの業界にいたこともあり、大学で勤務するようになってからもずっと市民活動や地域づくり等の現場に関わり続けてきました(それ自体が研究活動の一環にもなっていますが)。今回は、現在私が研究と実践の両面で力を入れている、脱炭素地域づくり分野での「中間支援組織」の活性化に関する取り組みについて紹介させていただきます。
ここ数年、日本では地域内での二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指す「カーボンニュートラル宣言」を行い、脱炭素化を通じた地域課題解決ならびに地域社会の発展を視野に入れた取り組み「脱炭素地域づくり」に着手する自治体が増えています。このこと自体は歓迎すべきことですが、具体的な取り組みを着実に進展させる上では課題が山積しています。特に深刻なのは、自治体において政策・事業のノウハウや人材といった「知的・人的基盤」が脆弱な状況にあることです。これまで国内の大半の自治体は、再生可能エネルギーや省エネルギー事業などを専門的に担う組織の整備や専門人材の確保・育成などにあまり熱心ではありませんでした。そのため、脱炭素地域づくりに着手することにしたが、実際にどのような取り組みを実施すればいいか分からない、コンサルタントの力を借りて計画は作ってみたものの、それを実行に移せない、という状態の自治体が多数存在しています
私が参加している研究チーム(研究者+NPOや中間支援組織に所属する実務家などで構成)では、このような課題を打開していく上で欧州の「エネルギー・エージェンシー」(以下、EA)という中間支援組織が参考になると考え、約10年にわたり現地を訪問して関係者へのインタビュー調査などを重ねてきました。重点的に調査してきたオーストリアやドイツでは、主に州や広域自治体(郡)などの単位でEAの設立が進められ、自治体、市民、企業、学校など対象に多様な支援活動を展開しています。一連の支援活動の中では「自治体政策支援」が重点分野と位置付けられ、関連計画の策定・実行をはじめとする政策プロセスにEA職員が伴走し、助言、情報・ノウハウ提供、教育、会議のファシリテートなど、きめ細かい支援を行っており、両国での脱炭素地域づくりを展開していく上で重要な存在と位置付けられています。
オーストリアのエネルギー・エージェンシー (エネルギー研究所フォアアールベルク)でのインタビュー調査
一方、これまで日本では、EAのような地域・自治体を支える組織体制を戦略的に整備していく動きはほとんど見られませんでした。しかし、ようやくここ1、2年ほどになって、日本でも認識が変わり始め、国などが開催する脱炭素政策に関連する検討会議等などにおいて有識者から中間支援体制整備の必要性を指摘する意見が相次いで出されるようになり、昨年5月に閣議決定された「第六次環境基本計画」では、脱炭素地域づくり分野で同体制の検討を進めていくことが明記されました。さらに、いくつの地域・自治体では、先行的に中間支援体制・組織の整備に関する検討を始める動きも見られるようになっています。私もそうした地域で行われている検討作業などのお手伝いをさせてもらっています。
そんな中、私が参加している研究チームと全国各地で脱炭素地域づくりの推進に取り組んでいる環境NPO「気候ネットワーク」(私の以前の職場でもあります)は、「脱炭素地域づくり推進のための中間支援交流フォーラム」という企画を2023年11月から昨年12月までの間に3回にわたり開催しました。これは脱炭素地域づくり分野での中間支援活動・組織に関心をもつ関係者間のネットワークづくり、同組織の整備・強化に向けた気運の盛り上げなどを目的にしたもので、全国各地の現場の最前線で活躍している実務家、研究者など50名以上のメンバーが集まり、お互いの取り組みなどの情報交換、今後の日本での組織整備の方策に関する意見交換などを行ってきました。そして、一連の議論の成果を踏まえて、第3回フォーラムでは、日本における中間支援組織の整備のあり方や検討課題等をまとめた「脱炭素地域づくり推進のための中間支援組織のあり方に関する論点整理」を発表しました。

第3回中間支援交流フォーラム(開催地:長野県飯田市)
私は、このフォーラムの企画、議論の進行役などの役割を担いましたが、全国各地に自分と同じような問題意識や思いを有している仲間が多数いることを改めて確認することができる機会になりました。また、フォーラム会場のあちこちで参加メンバー間の新しいつながりが生まれたり、今後の活動活性化の戦略などについて活発な議論が展開されたりする場面を目にし、自身がこれまで研究・実践の両面でやってきたことに一定の意味があったと実感することもできました。
現在は、上記の論点整理をベースにしながら、今後の中間支援組織の強化に向けた取り組みの展開策と、そうした活動の中核的な担い手となる全国的なネットワーク組織の立ち上げなどについて検討を行っているところです。研究者の立場として、実践的な動きがどんどん本格化していく中でどのような役割を果たせるのか、明確な答えは見出せないまま動き続けている状況ですが、引き続き、欧州や国内各地の現場の動きや関係している方々の声などを丁寧に収集・整理し、国内での議論活性化に貢献していく取り組みなどを地道に続けていきたいと考えています。
※欧州のEAについては、的場信敬・平岡俊一・豊田陽介・木原浩貴(2018年)『エネルギー・ガバナンス:地域の政策・事業を支える社会的基盤』(学芸出版社)、的場信敬・平岡俊一・上園昌武編(2022年)『エネルギー自立と持続可能な地域づくり:環境先進国オーストリアに学ぶ』(昭和堂)などで詳しく紹介しています。
※本コラムで紹介している日本国内での中間支援活動・組織の動向等の部分は、平岡俊一(2024年)「脱炭素地域づくり中間支援組織の整備・強化に関する日本国内の動向」『気候ネットワーク通信』No,159の内容をもとにしています。
※フォーラムや論点整理に関する詳しい情報については、NPO法人気候ネットワークのウェブサイト(https://kikonet.org/activities/local/intermediary_support_for_decarbonization)をご覧ください。