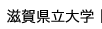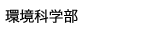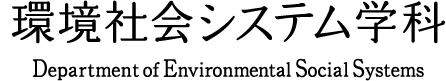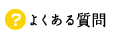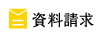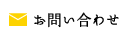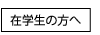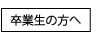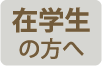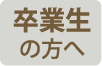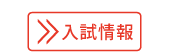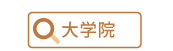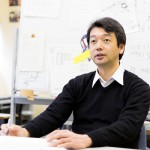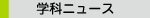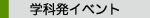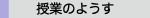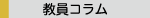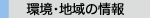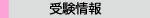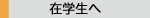東京の都心部におけるフィールドワーク 【香川雄一】
2024年12月27日(金) 01:54更新
今年(2024年)の9月に、東京のOJ大学で「フィールドワーク」の集中講義を実施してきました。滋賀県立大学環境科学部には1年生から3年生にかけて、「環境フィールドワーク」という授業があり、1年生と2年生は必修科目なので、学部学生全員が履修する授業です。滋賀県立大学周辺の「環境フィールドワーク」とは異なり、東京の都心部における「人文地理学」のフィールドワークです。おもに4月から7月に開講される前期科目としての「環境フィールドワーク」とは違って、たった3日間の短期集中型の授業ということに加えて、滋賀県の自然環境や大学キャンパスとは違う現場を歩くということから、その時の授業の様子を紹介してみたいと思います。
そもそものきっかけは、前に滋賀県立大学におられた先生が現在はOJ大学に勤めておられて、教員の交代時期の関係で1回のみの授業としての依頼が今年の初めころにありました。滋賀県立大学では、環境フィールドワークⅠ(1年生向け)とⅡ(2年生向け)を担当した経験があり、環境フィールドワークⅢ(おもに3年生向けで選択科目)も担当し続けていることから、フィールドワークの授業には慣れていたものの、滋賀県とは「環境」が異なる東京で、しかも3日間のみのフィールドワークの授業ということで、新たに授業の準備を始めることになりました。
授業の依頼があった時に、最初に思い浮かんだのは、5年ほど前まで担当していた、SG大学における教職科目の地理の授業に取り入れていたフィールドワークでした。彦根の城下町を見学して、現地で取材した成果を発表するという授業内容です。そこでの授業構成のヒントとなったのが、環境フィールドワークⅠの授業プログラムです。前期15回分の授業といっても、学部の1回生が4グループに分かれて、4つのテーマを受講しています。そうすると、最初のテーマは3回で、2回目以降のテーマは4回(×3)と、一つのテーマのフィールドワークは3~4回で受講していくことになっています。2回目の授業に現地見学をすることが多いので、初日はフィールドワークの準備、2日目は事前説明と現地見学、3日目はフィールドワークのまとめと発表という授業内容になっています。SG大学は彦根城のすぐそばにあり、半日もあれば歩いて城下町や地方都市の中心部としての機能となっているような公共施設を見学することができます。東京の都心部でもテーマさえ見つかれば、3日間でフィールドワークの授業を実施できそうだと考えました。
もう一つの過去の経験は、20年以上前に、AGJT大学で「人文地理学演習」の授業を担当していた時に、学期に1回は東京の街歩きのフィールドワークを実施していたことです。キャンパスが渋谷の近くにあったので、繁華街を見学することもありましたし、少し長い距離を歩いて、当時は完成したばかりだった六本木ヒルズの超高層ビルにも見学に行ったことがありました。

東京都心部のフィールドワークで対象とした範囲
授業の構成案はほぼ見通しがついたので、次はフィールドワークのテーマと歩くルートをどうするのかについて考えなければなりません。意外に思われるかもしれませんが、東京の都心部、とくに山手線の内側を歩く時には坂が多いことを実感します。NHKの「ブラタモリ」でも取り上げられていたことがありました。普段、地下鉄やJRなどの鉄道に乗って通学することの多い、東京の大学生たちに、フィールドワークで「坂の上り下り」を経験してもらうことが、現場を歩くことの重要性を伝えられると思いました。「環境フィールドワークⅠ」の授業の時と同様に、地形図で歩く場所の標高や等高線、土地利用などを確認しておくことも、授業の準備として伝えられそうです。
次に「人文地理学」のフィールドワークであることから、「地域の産業」も見学できればと思いました。東京は大都市として人口が多いのですが、京浜工業地帯の一部として、工業も盛んなのです。高度経済成長期以降の産業の空洞化や都市の再開発によって、多くの工場は郊外や地方さらには海外へと移転してしまいましたが、古い地形図や街並みを歩いてみることで工業の名残を見つけられることができるかもしれません。とくにOJ大学がある文京区は日本国内において、出版・印刷業の集積で有名だった場所です。事前の下調べから「印刷博物館」もあることが分かったので、フィールドワークの途中に博物館の見学によって地元の産業の学習も追加できそうだという見込みが立ちました。
さきほど超高層ビルの見学をフィールドワークに取り入れたことがあると述べました。東京をはじめとした大都市ならではの見学ポイントです。残念ながら滋賀県立大学の周辺には彦根城の天守閣くらいしか、高い場所からの景色は望めなさそうです。その点、東京にはたくさんの超高層ビルがある中で、「文京区役所」には最上階に展望フロアがあり、無料で見学できることが分かりました。学生の授業向けとしてもよい機会になりそうです。自分が歩いてきた場所を高所から振り返り、東京の景色を一望できることからも、受講生に楽しんでもらえそうだと思いました。
東京の特徴として、人口が多いことに加えて、著名人の足跡をたどることもできます。「環境フィールドワーク」ではなかなか思いつかないテーマでしょうが、人文地理学には文学作品と都市の関係性を調べる研究があり、小説の舞台として描かれた場所をフィールドワークで歩くことができます。2024年にちなんだ人物として、新札に登場する渋沢栄一に関する見学スポットも文京区外にはあったのですが、授業をする大学との近さを考えて、旧5,000円札の「樋口一葉」が住んでいた場所の付近を歩くことにしました。近くに「ふるさと歴史館」という文京区内の文学者について学べる施設もあったことから、休憩場所に使えるとともに見学することができると思いました。
いろいろとフィールドワークの見学ネタが集まってくる中で、何かオリジナルな見学ネタを紹介できないかという考えが思い浮かんできました。たぶん博物館や地域の産業関連施設は、小中学校の郷土学習や社会科見学でも思いつく場所でしょう。東京ならではのフィールドワークの見学ポイントとして、関東大震災後の震災復興事業や第二次世界大戦以後の戦災復興事業による都市計画があります。以前、読んだことのある都市計画の本で、OJ大学付近に「幻の都市計画道路」があることについて書かれていたことを思い出しました。フィールドワークのおいて身近な地域における意外な発見を用意しておくことも大事なことです。
こうして、授業初日はフィールドワークの概要説明と関連するテーマの紹介、2日目の午前中に文京区内のフィールドワークコースの説明と、午後の現地見学、3日目の午前中に前日のフィールドワークの成果をまとめて、午後に受講生全員が発表するという内容が固まりました。
ただし、授業期間が近づいてきた頃に、フィールドワークの実施時期に関連して、大きな問題があることを思い知らされたのです。滋賀県立大学の「環境フィールドワーク」でも季節の変化によって現地見学の印象は変わります。4月はまだ肌寒い印象で、5月くらいから歩くのが快適な季節になります。ところが6月は雨を心配しながらのフィールドワークになり、7月になると気温上昇で外歩きには熱中症の心配も出てきます。今回の授業は9月上旬なので、東京はまだ真夏の気候です。しかもコンクリートジャングルで、空からも地面からも暑さが迫ってきます。SG大学の授業も集中講義だったので、ほぼ同じ時期でしたが、歩く距離が短いのと、城下町という観光地だけあって、建物の中に入れば冷房で涼むことができました。AGJT大学の授業では、7月~9月という時期にフィールドワークを企画するという無茶なことは考えませんでした。
暑さ対策をどうするか、もちろん事前説明で、「環境フィールドワーク」の授業と同様に服装や水分補給については注意をしておきます。区役所や博物館に入れば冷房が効いているので涼むこともできるでしょう。しかし見学ポイントをルート上に設定して、ほぼ決まってきた移動距離の長さは、授業の構成から考えてどうしても削れません。東京の都心部を歩くことがどれくらい暑いのか、授業の一ヶ月半ほど前に下見で体験してみることにしました。歩くルートの候補を確認するためという目的もあったので、授業時よりは長い時間をかけたということもありますが、歩き始めてもう1時間くらいでこれは深刻な事態になる恐れがあるという不安を抱かせるような暑さでした。東京には高い建物が多いので、日陰を選んで歩いて、ごくまれに街路樹や川沿いの木陰を通れるということもありましたが、坂の上り下りの負荷に加えて、空気中を漂っているような熱気で、歩くルートの半分くらいの文京区役所にたどり着いたときには、展望フロアからの景色への期待よりも、涼めることと水分補給で生き返った感覚の方が重く感じられました。
これでは授業としてのフィールドワークの成立が危うくなりそうなので、事前に先方の先生とも相談して、東京のような大都市ならではの解決策を考えだしました。単純に途中で都バスを利用することです。ここでフィールドワークへのこだわりとして、地下鉄は使いませんでした。バスなら車窓から、歩いた時の景色を同様に見ることができるからです。念のため、バスの路線図と時刻表で想定していたルート沿いの路線と時間を調べたところ、乗り継いでいけば見学ポイントを授業時間内に回れそうだということが分かりました。唯一の心配は最後に使いたい路線が(東京の都心部でも)1時間に1本しかない路線で、授業の終了時刻から逆算して、そのバスの停留所に到着する時刻を目標に移動時間を設定することになりました。
こうして無事に授業当日を迎えることができたのです。見学ポイントを紹介しつつ、当日に発覚した反省点をまとめておきましょう。最初に歩き始めた時に、大学が立地する場所の地形も説明するつもりでした。(東京の都心部にありながら実は)丘陵部にある大学にありがちなのですが、OJ大学はキャンパス内が起伏に富んでいて、建物によって1階が入口となっている場所や2階から建物に入る場合もあります。滋賀県立大学にはバス停から人工的なスロープがあって、図書館や事務局の入口が2階にあるような感じです。OJ大学のキャンパス内で標高差が体験できる門からの出入りは、通常は閉鎖されているということで、別ルートを選択しなければなりませんでした。
大学からいったん坂を下って、急坂を上るところまでは体力もまだまだ残っていたので、心配ありませんでしたが、次の坂を下るときに工事中の看板があった時には、下見と違って驚きました。回り道も覚悟したのですが、工事をしていたのは最初の一部の階段だけで、無事に目標の川沿いまで、崖に設置された階段を降りることができました。

最初の急坂を登り切ったあたり

神田川によって削られた崖を下る階段
次のルートは印刷博物館までのバスの移動です。歩くと下見では30分以上かかりましたが、最寄りの停留所までは5分ほどで着きました。東京のバスは前乗りなので、25人ほどいた受講生も、奥まで詰めれば1回のバスで何とか乗り切ることができました。
印刷博物館の見学が今回のフィールドワークで最大のトラブルだったかもしれません。下見の時には問題なかったのですが、見学当日は館内の改装のため、半分ほどの展示しか見ることができず、肝心の文京区の印刷産業の歴史についてはほとんど学べませんでした。通常の休館日だけの把握では不十分だったようです。

かつて印刷業が盛んだった場所(道路の奥に見える高層建物の1階が印刷博物館)
続いてバスで移動して到着した文京区役所では、展望フロアからの眺望に加えて、2階にあった区政資料コーナーも見学できました。人数が多いことと時間が限られていることで、十分な資料調査まではできなかったようです。

文京区役所の展望フロアからの眺望
次のルートも急坂の上りなので、停留所の1区間だけバスに乗り、ふるさと歴史館を見学してから、樋口一葉の旧居跡付近に行ってみました。ここには昔ながらの水道ポンプがあるということで隠れた観光地になっています。しかしながら周りは普通の住宅地なので、25人もの大勢の学生が訪れたら、迷惑になってしまうかもしれません。半分ほどの人数に分かれて、路地の奥まで、静かに見学してもらいました。

樋口一葉の旧居跡付近
1時間に1本のバスに乗るために、余裕をもってバス停にたどり着けました。しかもバスが5分ほど遅れてきたので、手持無沙汰の集団が道路沿いでたむろするという光景になってしまいました。たまたま近くにスーパーがあったので、水分や食料を補給する買い物もできたようです。
最後の見学ポイントとしての「幻の都市計画道路」は、大学前の大通りに向かっての坂道でした。バス停を降りたところにあった坂の上り口付近には、印刷博物館を運営している会社とはまた別の、印刷会社の工場跡があり、再開発の高層マンションが建設中でした。東京の学生たちにとっては見慣れた光景かもしれませんが、日々変化する東京の街の様子を改めて感じたでもらえたと思います。幻の都市計画道路は中央分離帯が公園のようになっており、車道も歩道も道幅が十分にありました。こうした道路が都心部に張り巡らされていれば、東京の街の風景ももっと変わっていたかもしれません。歩いただけでは「幻」の部分が分かりにくく、前に示したような地形図で改めて、この部分だけに高規格の道路がある不思議さを理解してもらいました。

幻の都市計画道路の一部分
大学の最寄りの地下鉄駅で解散した時には、日が傾いていて、出発時と比べてだいぶ涼しくなっていました。普段とは違う行動パターンで受講生たちはきっと疲れたことでしょう。
翌日の発表では、地理学を学んでいる学生ならではの都市地理学的なテーマの設定や、スライドに地図や資料を用いることができていて、たった3日間の授業とは言え、よくフィールドワークの成果を習得できたものだと感心しました。授業への感想のなかで、改めて、滋賀県立大学の「環境フィールドワーク」の特徴に気づかされました。授業でいくつかの冊子から、滋賀県立大学の環境フィールドワークを紹介していたこともあるのですが、東京の都心部でのフィールドワークから経験できることの貴重さを学べたようです。授業としてのフィールドワークは観光客の行動とは違って、学習テーマが必要であり、学習の成果を発表に結びつけなければなりません。
フィールドワークの内容も大学が立地する場所に規定されます。もしかしたら滋賀県立大学の環境科学部の学生が、バスに乗って移動した先で見学しているかもしれない「自然環境」は、東京などの大都市の大学生には短時間の移動ではなかなか経験できないことなのです。都会にしかないものはすぐに気づくことができるかもしれませんが、滋賀県立大学の授業でしか得られないことにも、在学期間中により多く気づいてもらいたいと思います。