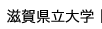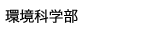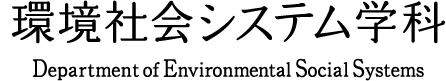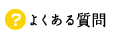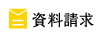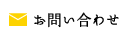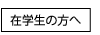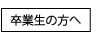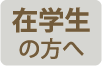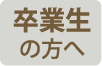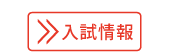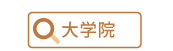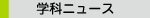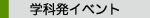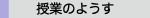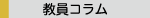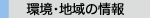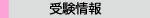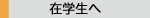琵琶湖で手塚治虫の聖地巡礼 【高橋卓也】
2025年05月09日(金) 01:26更新
琵琶湖の周辺でアニメやマンガの舞台を巡る聖地巡礼をしてみようと思います。ただし、今回は「けいおん!」の豊郷小学校ではなくて、(私たち昭和世代にとっては)少し昔のマンガ家・手塚治虫の作品です。
『火の鳥』は命の尊さ、はかなさを謳い上げる手塚治虫の超長編マンガです。火の鳥は不死鳥、フェニックス。その生き血を飲むと永遠の命が得られ、その羽根には治療効果があるという設定です。古代のエジプト・ギリシャ・ローマの頃から西暦3404年以降にまでに及ぶ時代を背景として、舞台はエジプト、ギリシャ、ローマ、日本、宇宙へと様々です。火の鳥は人間たちの愚かな争い、不死への願いを時を超えて見守るという役回りです。手塚の遺作となったこの火の鳥・太陽編は、7世紀の朝鮮半島と日本列島を舞台として、白村江の戦い、天智天皇、壬申の乱が登場します。主人公は百済王一族の兵士・ハリマ。戦に敗れた彼は顔の皮をはがれ狼の頭の皮をかぶせられます。その後、日本へとたどりつき犬上宿禰(いぬかみのすくね)として彦根邑(むら)を治めることとなります。彦根邑は、東方の蝦夷征服の経由地・八池邑(やちのむら)(14巻104、109ページ)から西に3里ということになっています(14巻171ページ)。古代の1里は500~600mとのことなので、八池邑は古代の官道・東山道を引き継ぐ中山道の高宮あたり、彦根邑は現代のJR琵琶湖線の彦根駅、南彦根駅、河瀬駅あたりのどこかと考えておきましょう。そうすると、滋賀県立大学近辺に来ると自動的に聖地巡礼となります。
犬上宿禰が治めた彦根を流れる犬上川はちょうど滋賀県立大学の横を流れています。電車通学をする県立大の学生さんは一日二回、行きと帰りで犬上川を渡り県立大学へと通学します。環境科学部の1回生は環境フィールドワークⅠで、じゃぶじゃぶと川に踏み込み自分たちの手で自然再生に取り組むので、一度は犬上川の水やアユなどの生き物と触れ合う機会があるはずです。私も通勤の際にこの川を渡るのですが、時々立ち止まるのは素晴らしい夕焼けが見られるためです。夕日が琵琶湖と犬上川の河口、そして琵琶湖対岸の高島の山々にかかる空と雲を紅色、橙色、藍色の豪華なグラデーションに染めつつ沈んでいきます。

犬上川河口から琵琶湖・多景島(たけじま)を望む
犬上川上流の山間部・多賀町には大瀧神社があり、そこにはこの地の豪族・犬上の君の先祖(日本武尊(やまとたけるのみこと)の子)を救った忠犬・小石丸の伝説が残っています。本学科の卒業生も地域おこし協力隊として地域おこしのために宣伝している「こいしまる」というかわいいキャラクターもいます。近くに毎年、環境フィールドワークⅡ「木と生活」で木造建築見学、キノコ観察でうかがっている高取山ふれあい公園というレクリエーション施設もあります。少なくとも一部の県立大生にとっては馴染みが深い場所でしょう。

「こいしまる」のトートバッグ
(2)三つ目がとおる 三つ目族の謎
超古代文明を繁栄させた三つ目族の子孫である中学生・写楽保介(しゃらく ほうすけ)が、三つ目族の遺産の眠る琵琶湖の湖底を探るため、1975年3月後半の飛び石連休を利用して、同級生の和登千代子(わと ちよこ)と琵琶湖を訪れるという筋書きです。なぜ三つ目族が琵琶湖の湖底に遺産を沈めたかについては、手塚は古代から湖であった琵琶湖は地質的に安定しているからという理屈付けをしています(第9巻68ページ)。
写楽保介「そう 琵琶湖は約150万年前にできた断層の陥没(かんぼつ)湖で 火山もないから その湖底は安全なんだ はかりしれない大むかし…… ボクたちの先祖たちは そこへ遺産をしずめた」※
※ 現在のところ、琵琶湖が現在の位置にできたのは40万年前とされています。
約6万ヘクタールある琵琶湖のどこを写楽クンと和登さんが訪れたかについてですが、これは間違いなく琵琶湖の最北端方面です。マンガの中でも余呉明神、つづら尾崎といった名前が出てきます。余呉明神という神社は実在しないようですが、琵琶湖の北方に余呉湖はあり、葛篭(つづら)尾崎は琵琶湖の最北端にある岬の名前です。琵琶湖の最北端へは、自動車か、自転車か、JR北陸本線・湖西線の近江塩津駅から徒歩40分ほどでたどりつけるでしょう。
この近辺には静かな湖面が広がります。沖に出ると水の女神・弁財天を祀る竹生島があります。「竹生島(ちくぶしま)」というお能の演題があります。ミシガン州立大学連合日本センターの学生さんと琵琶湖の北にある山門(やまかど)水源の森という自然公園に向かう車中、竹生島を眺めつつ、同行した滋賀県立大の能楽部の学生さんに「竹生島」の謡を歌ってもらったことが思い出されます。そういえば、この(2025年)3月には、参加学生のリクエストで、タイの東北部にある湿地に浮かぶカムチャノートというヘビの神様(ナーガ)をまつる島を訪問したことも思い出しました。弁財天は同時に竜神でもあることを思い出し、タイと日本とでつながるものを感じます。

北琵琶湖の湖岸からみた竹生島

タイ東北部・カムチャノートの島に渡る橋
アジアフィールド実習2025 タイの学生とともに持続可能な発展について現場で学ぶ
先ほど話に出た山門水源の森についてです。ここはもともと近くの集落の共有林で薪や炭用の木材を生産していました。さらにいうなら、琵琶湖の北の方(湖北)では100年以上前までは燃料用の木材を生産し、大津へと船で運んでいました。そしてそれらの燃料とする木材は、京都へも運ばれていました。湖北の森は京都の燃料基地でもあったのですね。運搬船である丸子船は、復元した船体を大浦の北淡海・丸子船の館や塩津の「あじかまの里」で見ることができます。丸子船は日本海から琵琶湖を経由して京・大坂へ物産を運ぶのに使われていた、かつての日本経済の大動脈です。
松下幸司・高橋卓也(2018)生産森林組合設立以前の共有林における山林経営―長浜市西浅井町三ケ字共有林の場合―.入会林野研究,38:77-89.
※ 2025年4月1日より入館料が改定されています。一般 改定前300円⇒改定後350円 小中学生 変更なし
ところで琵琶湖の深呼吸ということばがあります。琵琶湖の湖底の水が雪解け水の流入によって表層に循環し、湖底に酸素が補給される現象です。近年、地球温暖化の影響もあってか、深呼吸が起こらないこともあり懸念されています。湖北は豪雪でも有名で、福井県との境に近い菅並(すがなみ)は真冬になるとお天気ニュースで多い時で約2メートルの積雪が報告されます。フィクションの中の設定ですが、三つ目族の遺産の眠る琵琶湖湖底へとまわりの山々から雪解け水が流れ込むのを想像しながら静かな北琵琶湖の岸辺に立ってみるのも良いのではないでしょうか。
7月には滋賀県立大学のオープンキャンパスがあります。秋の行楽シーズンには彦根や長浜に来られる方もおられるかもしれません。手塚マンガを予習したうえで聖地巡礼もしてみませんか。