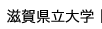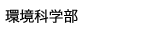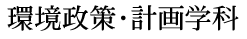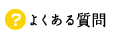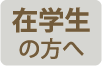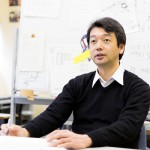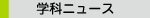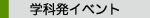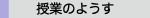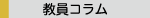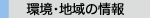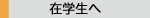「ホープ」から「ギャング」に落ちぶれた琵琶湖の外来魚 【香川雄一】
2025年11月28日(金) 02:58更新
2017年度の学部報(「自然」の構築と琵琶湖の「自然」,滋賀県立大学環境科学部 環境科学研究科 年報,22,pp.10-13 (2018))と、2023年度の本コラム(かつて「琵琶湖のホープ」と紹介された外来魚<https://depp-usp.com/archives/7190>)で、地方新聞での報道にみられる、過去の「琵琶湖の外来魚」に対する意外な評価について紹介してきました。今や「在来魚の天敵」、つまり琵琶湖の漁業者にとっては「迷惑な存在」となっている外来魚が、受け入れ当時は有望な水産資源とみなされていたことを、新聞記事等で確認しました。今回のコラムでは、地方新聞を読み進めてきた結果,評価の転換点にあたるような時期を特定できるようになったので、かつては「ホープ」とされていたのに、いつから琵琶湖の外来魚が「ギャング」と称されるようになったのかを説明してみます。
これまでの学部報の記事と学科教員コラムを振り返っておくと、新聞記事によると1966年から1972年の時点では、外来魚はまだ「琵琶湖のホープ」という存在だったのが、1984年から駆除事業が始まったということで、その間に評価が逆転したのだろうということを予想していました。駆除事業が始まるきっかけとして、1980年代に入って大量発生したという記録(中井克樹:琵琶湖の外来魚問題―歴史と展望―,地理,54(4),pp.58-67 (2009))からも、1970年代後半の新聞記事を探せば、逆転の証拠を見つけられそうだと考えました。そこで、京都新聞の滋賀版を中心に、毎年の記事をめくってみました。以下、新聞記事を引用する場合、漢数字を算用数字に、元号年を西暦年に書き換えたところがあります。
1973年、1974年、1975年、1976年と読み進めていき、なかなか探している記事が見つからないと不安になっていたところ、1977年1月17日の夕刊11面に「ブラックバス 湖を乗っ取る」という外来魚が悪者っぽくなった見出し記事を見つけました。サブタイトルには「ワカサギひん死 アユもえじきか」といかにも漁業者が困りそうな問題です。記事の導入部分には「稚魚を食い荒らし“湖のオオカミ”とまでいわれているアメリカ産の魚、ブラックバスが最近異常繁殖し、冬の風物詩、ワカサギ釣りが全滅の危機にさらされている。」とあります。「湖のオオカミ」という外来魚の別称は初めて知りました。さらに「この外来魚、針にかかると猛烈な闘争心を発揮、その手ごたえから太公望には大の人気者になっているが、水産関係者らは、強すぎるバス対策に頭を痛めている」と、後の釣り愛好家と漁業者の対立を予想できるような紹介となっています。ちなみに言わずもがなかもしれませんが、「太公望」というは中国の故事にちなんだ釣り人のことです。
記事の内容を詳しく見ていくと「ルアーフィッシング(西洋偽餌針を使っての釣り)が若い人の間でブームになると、対象魚としてバスがもてはやされ出した。関西では1973年ごろ釣りファンの一部が兵庫県の東条湖に投げ込んだのが繁殖のきっかけらしい。」とあります。その影響として「いまでは小さなため池でも姿を見せるほどに繁殖、持ち前のどう猛さで湖にいた魚を駆逐し、“湖のオオカミ”的存在になっている。」と問題視されるようになったことが分かります。琵琶湖に関して触れられているところでは、「年間千トンの放流権アユをはじめアユの出荷では全国の80パーセントを占める滋賀県のびわ湖でもバスが問題化した。例年に比べ50トンばかり漁獲が減ったが、バスだけが原因とも考えられず、広い水域なのでそれほどの影響はないと湖岸の専業者は見ている。」と、1977年初めの時点では、琵琶湖においてはそこまでは大きな問題とはなっていなかったようです。ただし、「しかし北湖のアユ漁の定置漁具「エリ」や漁師の網に計10匹のバスがかかった。体長35センチの成魚で腹の中からアユ、エビが大量に出てきた。」と漁業者からの不安視だけでなく、「放置すると、やがてアユ専門業者三千人の死活にかかわる問題になると、滋賀県水産課は昨秋から「バスを釣り上げたらすぐに殺して欲しい」とバス撲滅を湖岸に指示、釣りファンクラブ、雑誌などに対してはバスの放流をしないように呼びかけている。」と、滋賀県の水産行政としての立場からは警戒はされていました。
なお、この記事が掲載された夕刊11面というのはいわゆる三面記事的な部分で、必ずしも滋賀県民向けのみというわけではありません。記事の紹介にもあるように、まだ琵琶湖ではそこまで問題視されていなかったようです。実際に、その次に見つけた外来魚関係の記事として、1977年11月1日の26-27面の見開きには、「転換期を迎えたびわ湖の漁業」という特集記事が組まれています。そこでは「出番を待つ外国産魚」として「ブラックバス」や「ブルーギル」が紹介されていました。最初の紹介記事にも「彦根市八坂町、滋賀県水産試験場では、びわ湖の魚はもちろん、戦後移入された外国産の珍種も飼育され、近い将来“湖の紳士録”に登載される日を待っている。」とあり、外来魚の「ホープ」感がまだ漂っています。養殖を説明した記事にも「“捕る漁業からつくる漁業”へ。魚資源の開発も進んでいる。輸入淡水魚のテラピアニロチカも当然“出番”が待たれている。また、県水産試験場に飼われているテラピアジリー、ペヘレイ、ブルーギル、アスラ、テンチら新顔が登場する日も案外近いかもしれない。これらはまだ、食物関係、水温などを研究中で、びわ湖には放たれていないが、いずれも「うまい魚」といわれ、テラピアニロチカのように増殖される見通しもある。」と外来魚に期待が込められていることが分かります。
醒ヶ井養鱒場の開業100周年を紹介した、翌1978年1月3日の21面の記事にも、対象の魚種はニジマスとカワマスですが、「資源確保に奮闘の歴史」、「外来種の増殖、定着化に全力」、「200カイリで見直される」、「今後は魚病克服が使命」という見出しのように、「外来種」への悪いイメージは読み取れません。米国原産の外来種を日本に定着させようとしたことが「水産資源の確保へ地道な貢献を続けてきた。」と好意的に評価されているのです。
評価が反転したことは、同じ1978年4月12日の夕刊10面の記事ではっきりしました。見出しには「“びわ湖のギャング”根絶を」と完全に悪者扱いです。外来種に関しての評価も、いわゆる「オールドカマー」的存在は認めるが、「ニューカマー」は認めないというように、第二見出しには「新種魚類の外来ダメ」、「フナなど17種だけOK」とはっきりと線引きされてしまいます。政策としても「流入規則改正へ 県、水産庁と協議」とあるように、新たな外来魚への対策を始めようとしていることが分かります。
まず導入記事として「小魚を食い荒らす“湖のギャング”ブラックバスが琵琶湖で繁殖を続けているが、滋賀県はこのほど、外来新種のびわ湖流入(移植)を防ぐ規則改正を行う方針を決め、水産庁と協議に入った。」とありました。「出番を待つ外国産魚」と紹介されてから半年も経っていないのにもう厄介者扱いです。外来種同士の線引きについては「県の考えでは、びわ湖へ持ち込みができる水産動物として、ビワマス、コイ、フナモロコ、シジミ、タニシなど17種を条文に明記し、これ以外は知事の許可なしにはいっさいご法度にしようというもの。」と水産資源の確保を念頭においた区分が明示されます。除外された外来種については「「ブラックバス、ブルーギルなどの流入種がこれで根絶できるかどうかは疑問だが、被害魚のアユやエビなど、貴重な資源の保護に役立てたい」と県水産課で話している。」と説明されているように、とくにブルーギルについてはかつての滋賀県による水産行政の養殖対象が、漁業者も巻き込んで根絶対象に正反対の評価へと転換されてしまいました。
では、当時の琵琶湖で何の魚種が高く評価されたのでしょうか。記事には「びわ湖に生息する魚類は51種、貝類は43種(1971年、琵琶湖国定公園学術調査報告書)とされている。これほどの多種が共存している淡水域は、わが国では他に見当たらないが、」と淡水域における魚種の多様性が注目されるようになっていたようです。それに対して続く記事の文章では「ここ十年来、外来の“新種”ブラックバスやブルーギルが侵入しはじめた。特にブラックバスはコアユやエビなどを食い荒らす北米原産の魚食魚。1974年5月に彦根沖で見つかって以来、各地で発見されたため、1976年9月、県は各漁業協同組合に「発見すれば、ただちに連絡を」と要請し“ギャング退治”騒ぎとなった。」とされ、1970年頃までの琵琶湖とそれよりも後の琵琶湖で流入種、つまり外来種同士の線引きが画定されたようです。「侵入経過は不明だが、わが国では箱根・芦ノ湖で繁殖しているところから、釣り人が面白半分にびわ湖へ持ち込んだものとみられる。」とほぼ現在に続く外来魚に対する認識が固まってきたこともわかります。
外来魚対策において政策や制度の面からも記事には触れられていました。「こうした「市民権」のない外来種対策としては、法的には県漁業調整規則(1965年3月)があるだけ。同規則の「県内に生息しない水産動物の移植の禁止」条項(50条)では「県内に生息しない水産動物(卵を含む)は、知事の許可を受けなければ、これを移植してはならない」とあり、罰則は6月以下の懲役もしくは一万円以下の罰金。」とされていたようですが、懸念点として記事の続きには、「ところが問題のブラックバスが、現に百件を超すほど発見されている現状からすれば「県内に生息しない」魚にあたるかどうかが疑問となる。いたずら半分で持ち込んでも、この規則に違反しないとの見方が強い。」とあり、法的な対策が難しそうです。結果として上記のように、琵琶湖において「市民権を持つ」魚と「市民権を持たない」外来種という区分になったことが分かります。記事の解説部分では、「「市民権」を得た魚介類はびわ湖固有種が多く、事業として増殖を行なっているものを中心に選んだようだ。」というように、「在来種」を擁護しようという発想も生まれてきていたようです。
こうして問題視され始めた外来魚は、次に引用する記事の翌1979年の年末にはさらに事態が悪化しています。1979年12月27日の16面には、見出しに「びわ湖の“ギャング”」、「ブラックバス 全域で繁殖確認」とあり、刑事事件の犯人を扱うような紹介です。さらに「小魚を食い荒らす」「最大の収入源 アユ苗出荷にも打撃」と被害状況がアピールされています。しかも「県水試はお手上げ」と当時における事態の深刻化が伝わってきます。
これまでの記事と同様に、ブラックバスの「出自」や「性格」が紹介されていることに加えて、琵琶湖との関係では「5年前の1974年5月、彦根市内の湖岸で追いサデ漁の網にかかったのをはじめ、1976年には湖北、湖西のエリやヤナ、追いサデ漁で16件の捕獲報告が県水産試験場=彦根市=に寄せられ、さらに1979年には南湖でもコイやフナ釣りのサオで釣り上げられたり(原文ママ)大津市内の県文化館水族館の網にかかるなどすでにびわ湖全域にかなり繁殖していることが確認された。」と具体的な情報が集められています。
当時の対策として「県水産試験場や県水族館でもバス対策を検討しているが、せまい水域なら網入れや水抜きで根絶できるが、広大なびわ湖では、これといった妙案もなく、自然界の均衡がどの程度の繁殖を許すのか見守っていくより仕方がないという。」と、お手上げ状態だったようです。しかし漁業者にとっては外来魚の増加は困るようで、「被害魚の中で最も心配されるのが、びわ湖漁業の最大の収入源であるアユ苗。全国に出荷させるアユ苗は年間約300トン、約10億円の水揚げを誇っているだけに悩みも深刻」として、県鮎苗漁協組連ではアユ苗の増殖で保護を検討していました。こうして漁獲対象魚を守ろうとする漁業者と、外来魚の繁殖を支持する釣り客との対立構図が成立していったのかなと思います。
このように外来魚対策として、1978年の2~3月頃が転換期であったことを理解できました。ところで1977年~1979年の琵琶湖で何が起きていたのかを滋賀県の環境問題の年表で調べてみると、まさに赤潮問題に揺れ、大規模なせっけん運動が始まり、1979年10月には「琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が公布されています。公害問題などの汚染対策として認識されるようになった琵琶湖の環境問題が、後の生態系保全や生物多様性の保護といった環境再生に向けても展開し始めた時期ともいえるのではないでしょうか。
新聞記事をめくる作業は単純で、毎日のことだと見過ごしてしまっていることもあるかもしれませんが、あるテーマを定点観測として時系列的に調べていくと、思わぬ発見をもたらせてくれることがあることを、改めて認識することができました。
これからも環境政策・計画、改め、環境社会システムの歴史的な変化を、何かの素材を通して浮かび上がらせられれば良いなと考えています。