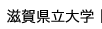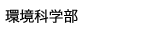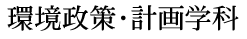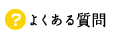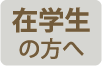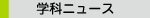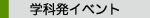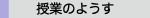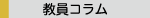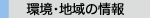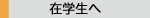環境科学部の目指すものー私の環境学ー 【井手慎司】
2014年05月15日(木) 09:31更新
確かそれはロバート・キャパについての逸話だったと思う。キャパはスペイン内乱から第2次世界大戦、インドシナ戦争にかけて活躍した戦争カメラマンだ。そんな彼があるパーティに、胸に一風変わったバッジをつけて現れた。バッジには「ただ今失業中」と書かれていた。パーティーの最中、喜々としてそのバッジを知人たちに見せびらかす彼の姿があったという。
キャパの活躍した1930年代から50年代とは、毎日のように地球上のかならずどこかで銃声が鳴り響いているような、そんな時代だった。彼は常に戦火の第一線にあった。そして写真を撮り続けていた。そんな中ほんの一時訪れたであろう平和な日々、戦場に立たなくてもよい、自分が戦争写真家として失業中であることの喜びが彼をそんな行動に駆り立てたのだろう。
キャパは初めジャーナリストを志したと言う。しかし、彼は言葉という壁を越えて万人に訴えることのできる写真の道を選んだ。彼が執拗なまでに悲惨な写真を撮り続けたのは、戦争がどれほど愚かな行為であるかということを世界中の人々に伝えたかったからだ。カメラという武器によってこの世の中から戦争をなくしたかったからだ。それが戦争カメラマンの使命というものだろう。だからこそ彼は、自分が失業中であることを喜んだ。
ではわれわれ環境分野に携わる者たちにとって、その使命とはなんだろう。環境科学部はいったい何を目指しているのだろうか。確かにわれわれは、少しでも環境問題の解決に寄与できるようにと日々、研究努力している。教育面では、環境分野のプロフェッショナルとなるべき人材を育成しようと努めている。しかし結局それらは何のためだろう。最終的には「環境問題のない社会」を創りたいからではないだろうか。
もし仮に世の中から環境問題というものがなくなったらどうだろう。われわれのような環境の専門家は必要でなくなるのだろうか。環境科学部のような学部はいらなくなるのだろうか。なくなるとすれば、われわれも戦争カメラマンのようなものかもしれない。自分たちが失業するような理想的な社会を目指して、そのために必死に努力しているのだから。とは言っても、本当にそんなバラ色の日は来るのだろうか。たとえ来たとしても、環境のプロが必要でなくなるということがあり得るのだろうか。
人間は生きている。生きている以上は、常に環境に働きかけている。例えば、私が一本の花をつみ取ったとしよう。すると他人はもう同じ花を摘むことができない。人と環境とはそんなゲシュタルト(図柄)の関係にある。例え人間が介在しなくとも、自然は常にエントロピーの増大の方向に向かおうとする。結局、人は環境問題を解決するために常に努力し続けなければならない。すなわち「環境問題のない社会」とは、状態として環境問題がないばかりではなく、生まれようとする環境問題とそれを解決しようとする努力が均衡を保っている社会でもある。ならば解決しようとする努力に環境のプロが必要であり続ける、という考え方も当然なり立つのである。
確かに一つの考え方としては、テクノロジーであるとか、それを駆使する一部のプロたちの手によって環境問題を解決していこうとするやり方があるだろう。例えば、流域下水道のような考え方だ。流域下水道は、多くの排水をまとめて処理しようとする。確かにそのほうがスケールメリットがあり、一面、効率的でもある。しかし、そのようなやり方だけで今の環境問題がすべて解決できると思うほど私は楽観主義者ではない。やはり、起こってしまってからの解決には限界がある。問題が起こる前に、その発生源で起こることを未然に防ぐような、すなわちゼロエミッションのような考え方がどうしても必要になる。また、よく言われるように、人間は自分たちが自然の大きな物質循環のなかの存在であることを認識しなければいけない。当たり前の話しだが、使ってしまった天然資源はもう元へは戻らないのである。循環系を維持するために、自然からの搾取は最小限にとどめなければならない。これらの考え方をわれわれの暮らしの中で実践しようとすれば、それは各家庭におけるゴミの減量化であったり、省エネ、省資源やリサイクルであったりする。より汎用的に言えば、各個人が常に環境意識を持ち、自分たちの生活や行動を律するということだろう。この観点に立てば、もはや環境のプロなどは必要でなくなる。あえて言えば、すべての人々が環境のプロとなるのである。
しかし考えてみれば、上記のように地球環境問題の解決にむけて個人のライフスタイルの変革やパラダイムのシフトが必要であると叫ばれるようになってから久しい。だがどうも、それらの声は人々の心にまでは届いていないようである。叫ばれる地球環境の危機も、多くの人々にとっては、どこか他人事のようである。
これに対して従来の心ある環境のプロたちは、旧約聖書にでてくる予言者のように警鐘を鳴らしてきた。神の声だとして「このままではいけない。地球に未来はない」と人々の危機感を必死であおってきた。しかし、あおればあおるほど人々の心は堅く閉ざされていくようである。繰り返される警告というものは、ともすれば人々の危機感を麻痺させてしまうものだ。要するに、いやな話は聞きたくないものである。ならば、もっと大きな声で叫べばいいのか。ところがそんなやり方には大きな落とし穴がある。それは子供たちがそんな話をどうとるだろうか、という問題である。大人たちにとっては聞き飽きた地球環境の危機も、子供たちの純粋な心にとっては、自分たちには絶望の未来しかないと映るのではないだろうか。たとえそれが真実の託宣であっても、子供たちに絶望だけを与えるようなやり方が正しいとは思えない。大人たちが心を閉ざす原因も案外そんなところにあるのかもしれない。
むしろ今求められていることは、環境問題がない未来-そんな明るい未来が来ることを信じることではないだろうか。これからの環境のプロに、もしその存在意義があるとすれば、それはむしろ、こうすればそんな明るい未来が訪れるのだという高いvisionを掲げて人々を導いていくことではないだろうか。
その意味において私は、この学部を卒業する学生がいわゆる環境分野というものに就職する必要は特にないと考えている。これはそんな所へ就職するなと言っているので決してない。どんな職業につこうと、どんな仕事をしていようと、この学部で学んだ精神-環境を大切にするという心-を忘れないことがもっと大事だと思うからだ。
橋をかけ、建物や道路をつくる。街をひらく。それらの計画をたてる。作物や家畜をそだて、人に奉仕する。なんでもいい。どんな職業でもいい。それぞれの立場のなかで未来を信じ、精いっぱい環境を守ろうと努力する、そんな人にこの学部の卒業生たちにはなって欲しいと思う。そのような姿を周りに示すことこそが、これから求められる環境のプロの姿だと思うからだ。
そして、われわれが目指す究極の社会とは、やはり「環境だけの専門家」などが必要でなくなる社会でなければならない。われわれは環境のプロとして、「ただ今失業中」というバッチを喜んでつけられるような、そんな社会を目指すべきである。
(『環境科学部 年報 第1号』 1997年3月31日)