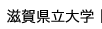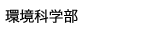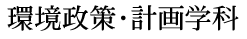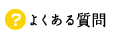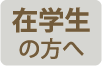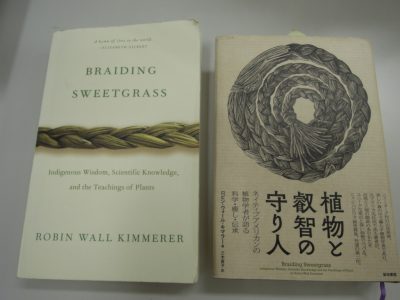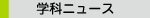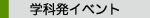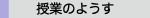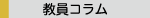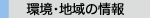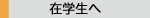スイートグラス・「入江る」・贈り物【高橋卓也】
2018年09月06日(木) 04:26更新
2008年夏、人間学科目(本学の教養科目的な授業)「異文化理解A」で、滋賀県の姉妹自治体であるアメリカ・ミシガン州を学生とともに訪れた。そのときのプログラムの一部でアメリカの先住民(ネイティブアメリカン)オジブワ族のお話をうかがったことがある。お土産としていただいたのがスイートグラスの三つ編みだった。その甘い香りを思い出しながら、ロビン・ウォール・キマラー著、三木直子訳『植物と叡知の守り人 ネイティブアメリカンの植物学者が語る科学・癒し・伝承』(築地書館)を読んだ。原題は、「スイートグラスを編みながら:先住民の知恵、科学的知識、そして植物の教え」である。
スイートグラスは、乾いた状態だと畳のイグサのような質感で、「ハチミツを垂らしたバニラが重なった香り」(本書3ページ)をもつHierochloe odorata(芳醇な、聖なる草)という学名の植物だ。著者は、アメリカ・ニューヨーク州在住の先住民女性の植物学者。二人の娘さんのうち一人は本書のストーリーの進行につれて大学へ進学している。著者が、子どもを育て、菜園をつくり、メープルシロップを収穫し、近所づきあいをし、大学で教える―――そうした生活の物語とともに彼女が属するポタワトミ族の神話・伝説、受難、再生が語られる。
著者は、自分が教えているニューヨーク州立大学で「環境学概論」の受講生200人の学生にアンケートを取り、人間と環境の間にあるポジティブな相互関係についてどの程度知っているか尋ねたところ、「何も知らない」という答えが一番多いことに衝撃を受ける。水質汚濁、大気汚染、地球温暖化、種の絶滅などのネガティブな相互関係ならいくらでも知っているのに……。ポジティブな相互関係を思い浮かべることができないとしたら、どうやって「環境的、文化的な持続可能性の実現に向けて行動を始めること」ができるのだろうか?この本では、人間と自然との間のポジティブな関係の可能性を数多くの物語によって示している。
スイートグラスは、五大湖周辺の先住民の神話に登場する聖なる植物である。――世界の初めには、スカイワールドがあった。その下には海が広がっていた。スカイワールドからスカイウーマン(最初の人間)が舞い落ちてくる。雁、水鳥、カワウソ、白鳥、ビーバーといった動物たちに助けられ、スカイウーマンは大きな亀の甲羅に落ち着く。小さなマスクラットが命と引き換えに海底から持ち帰った泥をスカイウーマンは甲羅の上に広げ、そこから大地ができてくる。先住民の住む世界(タートルアイランド、亀の島)の始まりである。この神話からは、人間がこの世界の新参者であり、他の動物たちに助けられてきたこと、また人間がこの豊かな世界を形作るうえで一定の役割を果たしていることが読み取れる。スカイウーマンはスカイワールドから植物の種をもたらした。そのうち地上で最初に育ったのが彼らの言葉でウィンガシュク、すなわちスイートグラスで、その香りは「忘れてしまったことさえ知らなかった記憶が蘇る」ものとされている。この本は、現代人が忘れてしまった多くの知恵を思い出させてくれる。
先住民の世界観を示すものとして、彼らの言語の特徴がある。過去には、アメリカ合衆国政府の同化政策により先住民の子どもは強制的に親から引き離され、全寮制の寄宿学校で教育を受け、彼らの言語を話すと厳しく罰せられた。著者の属するポタワトミ族の言葉を流暢に話せる人の数は9人に減少してしまっている。著者は、本来の母語であるポタワトミ語を学び始めた。
(著者はオジブワ語(ポタワトミ語と類似している)の辞書をめくり、英語では名詞であるべき単語が動詞であることに混乱する。ここからは引用。)
「土曜日る」。フン!と私は辞書を投げ出した。いったいいつから「土曜日」が動詞になったのよ?「土曜日」は名詞に決まっている。再び辞書を手に取って頁をめくると、他にも色々な動詞があった―――「丘る」「赤る」「長い砂浜る」、そして「入江る」。…
「こんなに複雑にする必要がどこにあるの。どうりで話す人がいなくなるはずよ。こんな言語、面倒臭いし覚えられやしない。それより何より、間違っているじゃない。入江っていうのは、人の名前か場所を指すに決まっている―――名詞よ、動詞じゃない」
そのときである。誓って言うが、頭の中でシナプスがビシッと音を立てて発火したのを感じたのだ。電流が私の腕を通って指先から流れ出し、その言葉が載っている頁が焼け焦げそうなほどだった。その瞬間、入江の水の匂いがし、岸に水が打ちつけるのが見え、砂浜に寄せる波の音が聞こえた。入江が名詞なのは、水には生命が宿っていないと考えるからなのだ。入江が名詞だと考えると、それは人間に定義されてしまう。周りの岸に囲い込まれ、その言葉の中から出ることはない。だがwiikwegamaa、「入江る」という動詞は、水を解き放ち、生命を与える。「入江る」という言葉には、今この瞬間、生きている水がこの岸と岸の間に身を寄せ、シーダー(杉)の根やアイサのヒナたちと会話しようと決めた、という不可思議さが込められている。(本書の78~79ページから引用。)
この部分を読んで思い出したのが、地球の反対側、日本の滋賀県彦根市犬上川河口である。滋賀県立大学環境科学部1回生必修の「環境フィールドワーク1」では、4月から7月の毎週月曜の午後、フィールドワークを実践する。そのなかのDグループでは、犬上川の上流から下流の琵琶湖岸まで現地に足を運んで観察する。本学すぐ横の琵琶湖岸の河口部は、上流からの土砂の堆積・流出、琵琶湖の水位変動、外来植物を含む植物の繁茂によって、月ごとに、週ごとに姿を変える。「入江る」あるいは「河口る」さらには「犬上川る」を感じる機会となっている。生命のある犬上川を見続けているとも言えよう。この先住民の生命的・動的な世界観は現代人が忘れがちなもので、そのため自然の恵みと脅威に日常的に無頓着になっているのではないだろうか。
著者の授業もフィールドワーク形式だが、より本格的なようだ(「大地に抱かれて」286ページから)。卒業要件科目「民族植物学」では、5週間、携帯電話の電波がつながらないような田舎でカエデの木、樺の木、トウヒ(針葉樹)の根、ガマの葉を使ってウィグワムというドーム型の家を作る。ガマは、ウィグワムを作るための紐、糸、日焼け対策ジェル、ゴザ、敷布団、食べ物として使い尽くされる。その作業をするなかで、学生たちに著者は問いかける。「カエデ、樺、トウヒ、ガマ」といった自然の贈り物に対して代わりに差し出せるものは何かと。感謝以外の義務はないのかと。学生からは、許可制度―収穫したものに対する料金を支払い、それが州に納付されて湿地保護に使われる仕組み、ガマの大切さについてのワークショップの開催、ガマを保護するため侵略種の除去、水の汚染防止のための天水桶の設置、芝生への施肥の中止、ガマをいつも思い起こすためのガマ製コースターの作成、などが提案される。著者はこのように語る。
学生たちは答えを持ち合わせないだろうと思っていたが、その創造性には頭が下がった。彼らからガマへの贈り物は、ガマが彼らにくれるものと同じくらい多様だ。自分には何を差し出すことができるのが、それを見つけるのが私たちの仕事だ。自分自身に与えられた才能がどういうものであり、どうしたらそれをこの世界のために使えるかを学ぶ。それこそが教育の目的ではないだろうか?(本書の308ページから引用。)
自然環境と人間との関係を考える人々にとって、この本のどの物語も立ち止まって耳を傾けたくなる、心に響くものだと思う。ご一読をお勧めしたい。また、この著者による前著『コケの自然誌』原題 「コケむしつつ:コケたちの自然・文化誌」築地書館―――は、本書と比べると自然科学の部分が多くて、しかし今回の本と同様、詩的な言葉で美しくつづられた物語である。こちらも手に取られることをお勧めしたい。