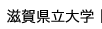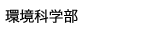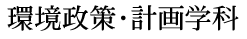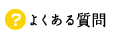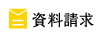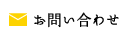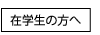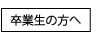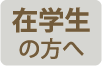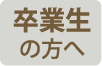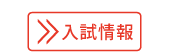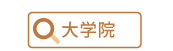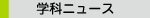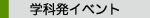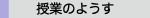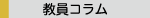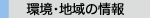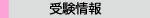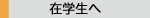卒業生、琵琶湖から大海へ 【平山奈央子】
2025年04月02日(水) 03:06更新
2025年3月20日、卒業式と謝恩会が開催されました。環境政策・計画学科では、今年度41名が晴れて卒業しました。4月から新たな環境で更なる活躍を期待しています。
卒業にたどり着くまでに、一番厳しい道のりであろう卒業研究について少しご紹介します。本学科では卒業研究は必修科目で全員が1人1つテーマを決めて、約2年間じっくり取り組みます。全体で共通するスケジュールとして、3回生の6月からゼミに配属し、卒業研究を開始します。3回生の12月頃に着手発表会、4回生の5月に1回目の中間発表会、4回生の10月に2回目の中間発表会(ポスター発表)、そして1月末に審査版卒業論文を提出し、2月に審査会があります。”審査版”というのは、本学科では査読の様なシステムがあり、指導教員以外の教員が卒業論文の全文を審査し、審査会での応答等を含めて学科全教員で全ての卒業論文を審査します。審査結果はS、A、B、C、Dで評価されます。もちろんSが最優秀賞で今年は3人が受賞しました。D評価だと再提出・再発表となります。
ゼミ配属では1研究室につき多くて5名くらいですので、先生1人に対する学生の数が少なく、ゼミごとに部屋やPCなどの設備があるのでとっても贅沢な研究環境だと思います。学年ごとにキャラクターがある様に、ゼミごとにも雰囲気や教員との関係性が違うような気がします。
過去の私のゼミでは、(私も含めて)名探偵コナン好きが集まったり、ゼミ室が夜中に麻雀会場になったり、ゼミ旅行があったりなかったりと、いろんな学年がありました。今年度は男子学生ばかりで、ダンスやウインドサーフィン、筋トレ、旅行など卒論以外にもいろいろ楽しんでいたようです。ユーチューバーもいました。卒論に全力投球ではなかったかもしれないけれど、大学生活を満喫している明るい人たちで良かったです。スケジュール管理では少しヒヤヒヤしたこともありましたが…。
研究者になるわけではないのに卒業研究が何に役に立つのか?と思う人がいるかもしれません。私は最後の発表会(卒論審査会)の講評で「新たなコミュニケーションのチャンネルを開通したと思ったらよい」と毎回同じメッセージを伝えます。どういうことかというと、卒論は、①先行研究のレビューをして何が明らかになっていないかを確認した上で研究の目的を設定する→②オリジナルのデータを集める→③集めたデータを分析し客観的に言えることを導き出す→④結果に対して考察する、の流れで進めます。このプロセスの中で、論理的に物事を説明する力、データを分析する力、思うように進まなくてもやりきる忍耐力などが身に付きます。これらの能力は仕事をする時にも使えます。自身の進めたいこと、売り出したいもの、主張したいことがあった時など様々なシーンがあり、上司、消費者、出資者など相手によって出し方・見せ方を変えると良いと思います。その中で、定量的データや定性的(質的)データを用いた説明に納得する人に対して、特に有効に働くと思います。そういう意味で、”コミュニケーションのチャンネル”と言っています。
大学では勉強以外にも地域での活動や社会経験などを積んだ人もいると思います。そういうもの全てが卒業生らの根っこ(基礎)を育てる栄養になることと思います。
卒業生のみんな、健康に気を付けて頑張ってください。
時々大学に遊びに来てくれると嬉しいな。
卒業おめでとうっ!!