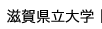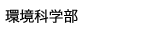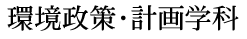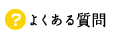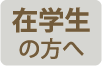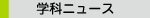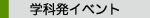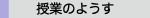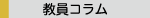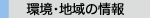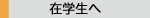ごみ問題についてー私の環境学ー 【金谷健】
2014年05月15日(木) 09:43更新
私は、3回生に「廃棄物管理論」及び「合意形成技法・演習」という授業をする。そこでこの小論では、ごみ(廃棄物)問題についての私の意見を述べる。ごみは、焼却などの中間処理を経て、最終処分される(一部はリサイクルされる)。最終処分は、山間部の谷間、あるいは海(大阪湾や東京湾など)を埋め立てて行われる。最終処分場の残余年数(=処分場残余容量/年間最終処分量)は、全国平均で約10年、滋賀県で約8年しかない(1993年度実績;厚生省)。しかもこれはあくまで「平均」であり、市町村によっては残余年数がもっと短いところも当然ある。
ごみ最終処分場の問題でむずかしいのは、「ごみ最終処分場は、土地(正確には埋立空間)を『消費』していく」という点である。処分場が満杯になったら次の処分場を探さなくてはならない、その処分場が満杯になったら次の……、というわけで、際限がないのである。これでは、「長期的なごみ管理」はできない。「処分場跡地を公園などに有効利用できるから、土地という形での『回収、リサイクル』だ」、と論じる人もおられる。それは事実だが、最終処分に適した場所(山間の谷間、海面)が次々に必要となるという点にかわりはない。
同じ「迷惑施設」でも、ごみの清掃工場(焼却や粗大ごみ破砕施設など)の場合は、最終処分場と違い、土地の「消費」という性格は持たない。清掃工場が老朽化(処分場の満杯に対応)しても、工場の建て替えができるからである。実際には、建て替えの期間中もごみ処理を継続しなくてはならないので、もうひとつ別の清掃工場用の土地が必要だ。ただし、この2組の土地でずっとやっていける。
現在、ごみ最終処分場の建設をめぐって、日本のあちこちで紛争が生じている。日の出町(東京・三多摩)が全国的に有名だが、県立大学の立地する彦根市でも新処分場建設についての紛争が生じている。こうした紛争は、今後増えることはあっても減ることは予想しにくい。山間につくれば自然破壊や水源汚染などの可能性は避けられないし、海につくれば海洋汚染や船舶航行への危険性などの増大の可能性が避けられない。それに山間も海(湾)も無限にあるわけではない。なお滋賀県の場合、海に面していないので、かなり厳しい状況にある。山間に埋め立てられなくなったら、琵琶湖に埋めるしかないからだ(県内の一部自治体は大阪湾フェニックス(広域最終処分場)に処分しているが、いずれそれも無理となろう)。
しかし、ごみ最終処分場は本当に必要不可欠なのだろうか? 昨年秋までは、「必要不可欠」が私の意見であった。「当然そうだ」と考えていた。しかし現在(1997年1月)では、「もしかしたら最終処分場が不要となるごみ管理が可能になるかもしれない」と考えるようになった。ごみの直接溶融を行っている茨木市(大阪)の事例を知ってからである。ごみの直接溶融では、ごみを高温の溶融炉(上部は300℃、下部は1500℃以上)の上部に少量のコークス及び石灰石とともに投入し、下部から溶融物(スラグ、鉄)が排出される。同市(人口約25万人)の1年間のごみ排出量が11.8万トン、溶融物量が2.4万トン(内スラグ1.5万トン、鉄くず0.9万トン)、最終処分量が0.6万トンである(1994年度実績)。重要なのはこの溶融物が、有価物としてリサイクルされている点である(265円/トンでかなり安価ではあるが)。スラグは道路舗装用土木資材等に、鉄くずは建設機械用カウンターウエイトに利用されている。
茨木市でも、溶融飛灰(集塵灰)だけは最終処分せざるをえない(上記0.6万トン)。同市には最終処分場が事実上なく、大阪湾フェニックスに最終処分している。しかし溶融飛灰のリサイクルの道筋もできつつある。(溶融)飛灰中の有害物は主に重金属であるが、それを分離回収して金属精錬業界に売却・リサイクル(山元還元)しようという技術開発が溶融炉開発企業で現在盛んに行われているからだ。有害重金属を有用重金属にするのである。この技術が実用化されれば、ごみ最終処分場は必要不可欠ではなくなる。
「『ごみを直接溶融し、溶融物及び溶融飛灰を有価物としてリサイクルする』ことによってごみ最終処分場を不要とする」というのは、ハードな技術でごり押しする考え方であり、カネもかかる。
*溶融炉は焼却炉より建設費も維持費も高いからである。ただしカネがかかるといっても、溶融をしていない他の自治体と比較して、茨木市が何倍もかかっているわけではない。せいぜい5割増くらいであろう。
カネがかかる以外にもいくつか問題がある。しかし最終処分場が不要になるかもしれないのは大きな魅力であり、実現可能性の検討が今後必要だ。
さて、ごみ(一般廃棄物)の最終処分場がもし不要になっても、もちろんごみ問題がすべて解決したわけではない。産業廃棄物の最終処分はもっと大変だし(処分量は一般廃棄物の約6倍あり、有害物も多い)、何よりごみの排出量そのものを減らさなくてはならないからだ。
ごみの排出量を減らすにはどうしたらいいか? 市民一人一人が環境意識を高めて「ごみを出さないライフスタイルにかえる」ことはもちろん大切だが、ごみを出すことにもっとカネをかけるのが一番効果的と考える。「ごみになる製品(容器包装材含めて)をつくる」企業からはカネをとり、「ごみをたくさん出す」市民からはカネをとるのである。現在、ごみ処理経費は一年間に国民一人あたり約1万8千円(1993年度)である。この経費は安すぎる。生産や消費がごみ(廃棄)によって大きな影響を受けているとは、とても思えないからだ。「こんなにカネをとられるくらいなら、ごみを出さないほうがましだ」、「こんなにカネをとられると、ごみをあまり出せない」というくらいのカネをとるべきと思う。それでようやく企業は、製品をつくる際にごみを出さない、製品がごみにならないことに本腰をいれて創意工夫をするだろう。市民も本気でごみ減量を工夫するだろう。
最後に。ごみ直接溶融をやって最終処分場が不要になっても、溶融施設という「迷惑施設」は依然として必要となるが、地元住民等の合意が簡単に得られるとは思えない。「迷惑施設」の建設はたいていの場合、ある日突然地元住民に知らされる。そしてその時にはすでに行政は後戻りできなくなっている。行政の末端の担当者は建設を前提にしか話せないから、地元住民の憤り(=自分たちの関知しないところで自分たちにとって大切なことが決められた、という憤り)に対して逃げるか無視するしかできない。こうした現状を所与として、「地元住民を説得する」あるいは「地元住民に理解を求める(嫌な言葉である)」ための道具として「合意形成技法」を使わないように、授業で学生に強調したい。「環境アセスメント」は「環境アワセメント」としばしば呼ばれている。「合意形成技法」が「合意強制技法」と呼ばれないようにするには、
*行政は地元住民に対して、「迷惑施設」立地場所検討段階からの情報公開、及び意志決定プロセスへの実質的参加を保証すること
*地元住民以外の大多数の市民や企業は、地元住民に「迷惑施設」という負担を強いるなら、自分たちはごみを減らす具体的行動(前述)をとるという負担を受けること
がそれぞれ必要である。
(『環境科学部 年報 第1号』 1997年3月31日)