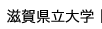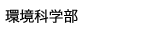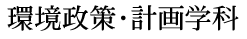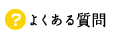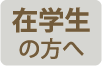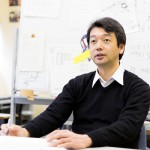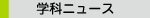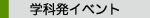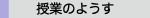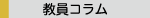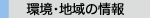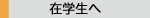工業都市における公害問題と地域社会の対応ー私の環境学ー 【香川雄一】
2014年05月15日(木) 09:40更新
「環境」への関心と地理学
1970年代初頭に誕生した私は、この時期が環境問題において大きな転機となっていたことを、後に知った。「公害国会」における各種法制度の制定、環境庁の発足、国連人間環境会議というように、「環境」への関心が高まっていく時期であった。もちろん幼少の折にはそのような時代情勢を知る由もなく、映画やテレビで環境問題を素材とした作品を目にしても、それほど感銘を受けた記憶はない。むしろ自分にとっての関心は、広い意味での「環境」、つまり場所による環境の違いや風景や文化を形成する身の回りの環境にあった。
少年時代に数度の転居を経験し、旅行や地図が好きだった私は、地理という科目に興味を持った。当時は就職への影響など考えもせずに、地元以外の地理学教室のある大学に進学した。はじめは漠然とした教科としての地理をイメージしていたのだが、研究室に所属するようになって大きな衝撃を受けた。今となっては、当然視できるようになった問題意識や研究方法の議論にまったくついていけなかったのである。しかも地理学は伝統的な調査手法と革新的な概念構築との間で大きく揺らいでいた。
卒業論文の着手に当たって、テーマを導き出したのは社会問題に地域社会がどう対応しているのか調査してみたいという問題意識であった。指導教官の助言も受け、原子力発電所が集中する福井県の若狭地方を調べることにした。滋賀県のすぐ近くである。
だが、問題が大きすぎたこともあり、満足のいく調査はできなかった。特に反省点として残ったのは、テーマ性を意識し過ぎたため、実態調査がおろそかになっていたことである。このことは大学院に進学してから卒業論文への痛烈な批判を受けて、改めて地理学の研究手法を習得し直すことにつながった。また調査対象に課題設定から向き合うという意味で、「環境問題」に取り組むことを決心した。
フィールドワークへの取り組み
学部時代に地理学の専門教育を受けていたとはいえ、フィールドワークの経験という意味では非常に幼稚な技術しか習得できていなかった。地理学は自然地理学と人文地理学に分かれており、環境問題に対してもそれなりに研究蓄積がある。しかしながら自分が調査していたことは、実は既存データの利用や資料に書いてあることの要約だけではないかという疑問が生じた。オリジナルな客観データの収集にどうやって取り組めばよいのか悩んだ末に、環境問題の歴史的変化を地域社会に視点を据えて眺めてみることにした。これが修士論文の研究テーマである。
地図や統計データの収集はもちろんのこと、古い新聞をめくり、文書館で資料をあさるということも経験した。また歴史的なこととはいえ、古い時代のことを知る人たちに話を聞きに行き、資料と照らし合わせながら事実を確認した。環境問題の調査と言ってもそれは今の問題意識であって、もちろん、水や空気が汚れれば生活に影響も出てくるが、生業や健康への被害が環境の悪化よりも高く意識されているのがよくわかった。このとき調べていたのが、現在に至るまで自分の研究フィールドとなる神奈川県川崎市の臨海部であった。
川崎の地域環境問題を事例として
川崎と言うと高度経済成長期の公害問題や埋立地の石油化学コンビナートがよくイメージされる。公害裁判やエコタウンとして注目されるのも同じく臨海部である。ここで環境問題がどのように発生してきたのかを知りたかったので、公害問題の端緒に着目した。川崎の工業化は、東京と横浜における経済活動の波及による工場の立地によって始まった。
日本の大都市周辺における臨海部は現在、ほとんどが工場地帯になっている。川崎市も例外ではなく、海水浴はおろか海辺に近づくことも容易ではない。昔は東京湾に面した遠浅の砂浜が、明治時代末期の埋立に始まり大正から昭和初期にかけて臨海工業地帯へと変貌したのである。
ほぼ時を同じくして大気汚染と水質汚濁の公害問題が発生していた。原因は工場からの排出物である。歴史資料からその場所を特定できたので、工場周辺の住民や地域組織がどのように対応したのかを資料によって明らかにした。観測データはほとんどなく、汚染と被害の因果関係も定かに示されていない時代のことである。それでも地域の有力者や産業組合、町内会レベルの住民組織が工場に対して異議を申し立てている。そこに環境問題への地域社会による対応のメカニズムを見出そうとしたのである。
100年ほど前の話で、しかも激しい都市化を経験した地域であったが、ある程度の事実は明らかになった。それでも調査方法が果たして妥当だったのかという不安を抱え、過去の環境問題を研究する意義について自信をもてなかった。その頃、依拠していた研究が米国の地理学者による社会運動研究への問題提起であった。
なぜ人びとは運動に参加するのか
学部の頃から社会学の社会運動研究は参考にしていたつもりである。それでもやはり地理学的な研究方法へのこだわりはあった。偶然、大学院の外書講読の授業で見つけた論文が、自分の研究を支えてくれることになる。そこでの問題意識は以下のようなものだった。
合理的な個人は本来、要望を受け入れてもらうために集合行為としての社会運動には参加しない。なぜなら参加の如何を問わず要求が実現するのなら、楽な方、つまり参加しない方を選ぶからである。それでも集合行為に参加するためには何かの理由がある。それを見定めていかなくてはいけない。社会運動への参加を説明するために政治経済的アプローチや歴史的アプローチが試みられた。地理学者はそれらに対して場所の特徴やコミュニティの役割に注目すべきであるとした。
川崎は東京湾と多摩川に沿って工場が立地した。京浜臨海工業地帯の中枢として空襲による戦災はあったにせよ、製造業において日本で有数の生産規模を誇っている。一方で工場労働者の流入と東京、横浜の通勤圏ということから人口も爆発的に増加した。こうした工業都市としての特徴のほかに、臨海部の農漁村が都市化、工業化を経験したがゆえの在来産業や地付住民の存在もある。それらが公害反対運動の形成に大きくかかわっていたのであった。
博士課程に進学してからは、方法論を学ぶとともに高度経済成長期を見据えて川崎の調査を継続しつつ、長期休暇の際には、別の地方における公害反対運動も調べてみることにした。そこで社会運動への参加の経緯を比較してみたのである。
場所と時代を変えて確かめてみる
公害反対運動における日本全国の動向を文献で調べながら、川崎以外の対象地域を倉敷市(水島)と和歌山市に選定した。選択理由に個人的な調査の都合(宿泊地、交通手段、協力者)があったとはいえ、川崎に対して地方都市であることや工場地帯の形成過程から、比較対象として適切であったと思う。
高度経済成長期の公害反対運動が調査の中心となったため、戦前の川崎に比べて資料は探しやすかった。しかも限られた住民に対してではあるが、実体験の聞き取りも可能であった。反対運動の展開に加えて、議会資料も分析対象とした。記録が残っていることで、公害問題への関心の程度やいかなる属性の議員が積極的にかかわっているのかを検証できた。川崎とは規模や時代背景が異なるものの、環境問題への地域社会による対応という側面では相似性を見出すことができた。
次の作業は川崎の過去をさらに遡ることと、現在に至るまでの公害反対運動の展開を跡づけていくことであった。公害問題が発生していない時期でも調査が必要なのは、場所の特徴やコミュニティ運営の中心人物を調べることができるからである。高度経済成長期の公害反対運動の分析では他都市で用いた議事録の分析に加えて、政治過程に影響する選挙の投票結果を集計してみた。いわゆる公害反対運動の主体イメージがどのように形成されてきたかを確認することもできた。
こうして調査をまとめつつ、2001年3月に学位を取得した。製本された冊子を手にとってみると、それなりの達成感はあったが、研究としてはまだまだ途上であることを思い知らされた。フィールドワークで抱えた疑問が目の前に立ちふさがっていた。他分野の研究との接合が、学位論文に加えなかったいくつかの調査のまとめ方を模索してみた。
学位取得後の課題と作業
政治地理の枠組みで研究成果をまとめるとともに、最初に取り組んでみたいと思ったのは、環境問題発生地における社会運動に参加しなかった住民の調査である。これは共同研究で川崎臨海部の漁業者に注目した。研究手法としては収集データをGISによって表現する技術を習得した。関心が近い研究組織に参加してアジアの大都市における環境問題に取り組みつつ、環境問題を景観の開発や保全といった視点からも解釈しようとしている。環境問題をテーマにしていることで、研究の幅は徐々に広がった。それを教育にどう結びつけていくのかも、授業では意識するようにしている。
「滋賀県立大学の環境学」への期待
着任地である滋賀県立大学環境科学部は職場としても居住地としても環境問題の研究に最適である。環境学諸分野の研究者や意欲を持つ学生・院生との議論を楽しみにしている。目の前に広がる琵琶湖と滋賀県の地域社会は魅力的なフィールドである。私の環境学は今、始まったに過ぎないのかもしれない。
(『環境科学部 年報 第11号』 2007年3月31日)