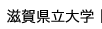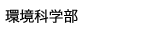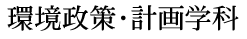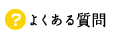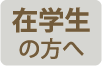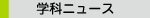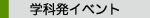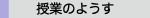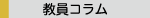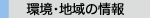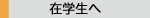私の環境学 【上河原献二】
2014年05月15日(木) 09:44更新
私は、昨年3月まで環境省にて、主に法律を中心とする制度の企画立案と施行に携わりました。水質保全、環境影響評価、環境白書、環境基本計画、大気保全、地球環境保全、環境税制、石綿健康被害、災害廃棄物対策、自然環境保全など多くの分野を担当してきました。その中でも特に長く携わったのが、国際条約交渉とその国内実施でした。国際条約は、国内法と比べて、分かりにくい存在です。しかも、日本の組織がジェネラリスト志向であるのと比べて、国際会議には諸外国から専門家たちが集まってきて、専門家コミュニティーを形成しています。何らかの形で専門家を日本も養成しなければ、国際交渉で不利になると感じました。国際化に伴う専門家の必要、はおそらく日本が多くの分野で経験している課題なのです。在ジュネーブ国際機関日本政府代表から1998年に戻ってきて、京都大学の西井正弘先生の研究会にお誘いいただいたのが、私の地球環境条約研究の出発点でした。その後、法学部・法科大学院で、地球環境条約の非常勤講師を計8年間務めました。役所業務の傍ら教壇に立つことは、きつい時もありましたが気分転換にもなりました。その後、2008〜2011年度、上智大学大学院地球環境学研究科に出向して教える機会を与えられました。その機会を生かして、地球環境諸条約の変化に関する類型論的研究で、博士(環境学)号を同大学からいただきました。
様々な地球環境条約の多様な変化を検討していく中で、私は、「権利-義務」を論ずる法律論だけでは十分ではなくて、制度変化を論ずるには政治学的視点も必要だと思うようになりました。ルールの変更は政治の役割です。その点で、私は、多数国間協力について生涯をかけて論じたアーンスト・ハース(1925-2003)という国際政治学の先生を尊敬しています。彼は、国際社会を形成する主体の行動を規定する要素として、「力と利益」を認めつつ、それに加えて、「知識」(理念や科学的知見)の変化を重んじました。客観的な外部要件に拘束されつつ人間は「知識」に導かれて歴史を形成していくことを主張したマックス・ウェーバーの伝統に、彼は立っていました。
1970年代以降多くの地球環境条約が採択されましたが、それらは、実施過程を通じて、様々に変化しています。大きな争いもなく無難に発展することもあれば、激しい対立と混乱におちいる場合もあるし、対立を乗り越えて新たな合意を形成していくこともあります。特に私が1995~1998年当時ジュネーブの国際会議場で経験した有害廃棄物の越境移動に関するバーゼル条約とアフリカゾウ論争を巡るワシントン条約における深刻な対立は、「国際協力のための制度において深刻な対立が起こるのはなぜか」という問を私に与えました。アーンストハースによる国際機関における変化の3モデルを適用することによって、それら多様な変化を説明したのが、「地球環境条約における変化の類型論」(2011)です。それをより一貫した論理枠組に従って大幅に書き換えたものが、Comparative typological study of change in global environmental regime (2013)です。国際機関と多数国間条約を峻別する見方もありますが、私は、横田洋三(2001)やB. B. Desai (2010) と同じく、多数国間条約制度は、定期的代表会合により管理され常設事務局によって支えらえた国際協力のための法的制度である点において、国際機関に類似する存在であると考えます。
またこれまで「条約の義務の履行」という形で、地球環境条約の国内制度への影響について多くのことが語られてきました。しかし、現実には、各締約国内の実施が国際制度に影響を与えることもあるのです。ワシントン条約における象牙貿易管理論争とそれに伴う国際・国内の制度変化はその典型です。条約の実施は、国際制度と国内制度が双方向に影響を与える過程なのです。日本が、地球環境条約制度において、1980年代前半までの受動的立場から積極的な立場に転換したことが、そのような観察を可能としています。それを論じたのが、「条約実施を通じた国内・国際双方向の変化-ワシントン条約実施を例として-」(2011)です。今、私より若い国際法・行政法の先生方がこの命題を中心的なテーマの一つとして、研究プロジェクトを進めておられるのはうれしいことです。私も、そのプロジェクトの一環として2013年12月開かれた公開シンポジウムにパネラーとして参加してきました。
現在、地球環境条約の実施とは何かについて、外来生物対策国内制度を素材とした論文を準備しています。多くの人は条約実施とは「義務の履行」とみなしていますが、「政策の学習・移転」でもあるというのが私の主張です。生物多様性条約における政策勧告的規定とガイドラインの策定を活用した日本における外来生物対策法制度の導入はそのよい事例です。
その次には、地球環境条約の締約国会議で広く採択されるようになった「戦略的計画」、「目標」というものについて、論文を書きたいと思っています。地球環境条約制度は、具体的環境分野についての国際協力を継続的に行う制度です。しかし、協力の進展に合わせて制度を見直していくにも、条約改正は容易ではありません。運動体としての地球環境条約制度の方向を再確認する手段として、「戦略的計画」、「目標」といったものが採択されるのだと、私は解釈します。この点について論じた文献は、私の知る限りほとんどありません。
先述の外来生物対策国内制度の検討を通じて、国際条約を通じたいわばトップダウンの方法は、大きな成果を挙げてきたものの、各地域への定着という面では限界もあることを、私は改めて理解しました。琵琶湖とその集水域という日本における環境政策の重要な現場に位置する滋賀県立大学で教える機会を与えていただいたので、実務経験を生かして、地域の環境問題についても考えていければと願っています。以下は、これから取り組んでいきたい課題です。
第1に、琵琶湖の湖畔やその集水域には、侵略的外来植物(ナガエノツルノゲイトウ、オオハナミズキンバイ等)やアカミミガメ、アライグマなど多様な侵略的外来種が現れ、生態系を大きくかえ生物多様性を損ないつつあります。それらに対処していくためには、国、県、市町村、漁業協同組合、NPO、研究機関など多様な主体の協働が必要ですが、まだはっきりした役割分担のルールはありません。自然科学・社会科学の諸先生方と御一緒に、地域における侵略的外来生物対策のあり方について考えていきたいと思っています。関連して、今個体数が増えて、森林や農業に被害を与えているシカ、イノシシなどの野生動物管理も、滋賀県と日本における自然環境保全の最大級の課題のひとつです。環境省(庁)野生生物課創設メンバーの一人として、野生生物管理(wildlife management)が、日本において確立されることを願っています。
第2に、日本各地で、個性的な手法により地方自治体の環境基本計画が策定されています。「計画には数値目標が大事」という意見をよく聞きますが、私は、国の第一次環境基本計画策定作業に携わって以来、そのことに疑問を持ち続けてきました。
ポスト計画経済、ポスト公共事業計画の時代における、社会を幅広く対象とした長期の総合的な計画の大きな役割とは、将来の課題の探索・設定とそれに基づく新たな理念・ビジョンの提示ではないでしょうか。大きな不確実性のある長期の社会の将来について数値目標で語れる部分はわずかでしょう。行政でも企業でも、「計画」より「戦略」という言葉が国内でも諸外国でも使われていることは、その表れだと思います。環境基本計画の計画論について、諸先生方とご一緒に考えていきたいと思っています。
第3は、動物園に関する制度についてです。日本において動物園の研究・教育機能については博物館法が、レクリエーション機能については都市公園法が存在します。今日、動物園は、希少動物の域外保全など自然環境保全に関する大きな役割を果たしていますが、それを支える法制度はないのです。また、欧米の多くの動物園は、各都市で設立された「動物学協会」が経営主体ですが、日本の動物園の多くは、地方自治体が経営主体です。日本の動物園の自然環境保全に関する役割を支える制度について、動物園関係の方々と一緒に考えていきたいと思っています。
多くの課題を並べてしまいました。多すぎるかもしれませんが、それらの夢を実現させるべく、多くの方々と協力して、またうまく時間を管理しながら、取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
(『環境科学部 年報 第18号』 2014年3月31日)