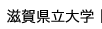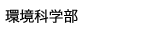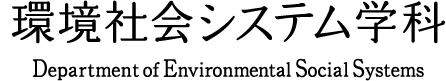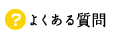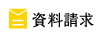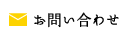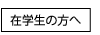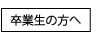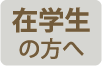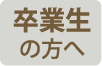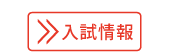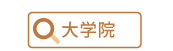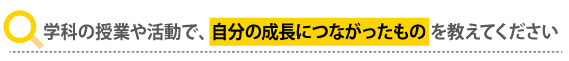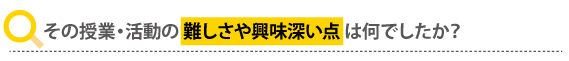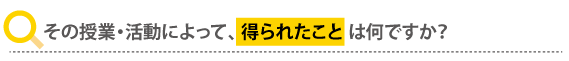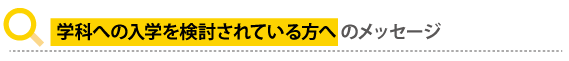矢野友季子 さん
2013年度入学


矢野友季子さん
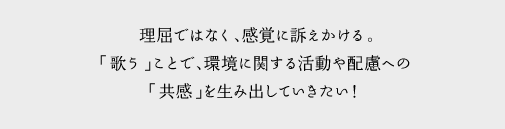
私は、この学科で勉強することを通じていろんなことをやってみようという力をもらいました。環境政策・計画学科では社会と環境について学ぶことが多く、さまざまな環境問題を解決するために活動する行政や住民、NPOといった「人」がとてもたくさんいることを感じました。また、私たち人間の生き方というのは、思った以上に多様性があるとわかりました。これは極端な例かもしれませんが、例えば、世界にはエコビレッジという最新の技術を使い健全な生活を追求しながらも地球に負荷をかけないような共同体をつくろうとしている地域があります。そのようなことを学んだことで、自分自身にもさまざまな生き方を選ぶことができるし、選ばなければならないと感じるようになりました。
今、私はある環境NPOの方のもとで歌手活動をしています。葦をテーマにした歌です。歌を通じて葦や水辺の環境のことを思ってもらえるように、ということを目標に活動しています。
私がやっている活動自体の難しさは、やはり1曲の歌を歌わなければならないことです。音楽としての表現と、歌詞を聞こえやすくメッセージを込めて発することを同時にこなさなければ何を伝えたいのかあいまいになってしまいます。歌詞には、「湖の母」(葦)の視点で水鳥や水辺の風景を見守り、自分も成長していく姿が描かれています。その意味が伝わらなければ歌う意味がないということになってしまうので、ステージで歌う時に気を付けています。環境に関する活動や配慮を広めるには「共感」というものが必要だと考えていますが、音楽は「共感」を生み出しやすいものであり、理屈ではなく感覚に訴えかけられるものであるということがとても興味深く、今後深く勉強できたらいいなと思っています。
この学科で勉強することによって、普段の生活や趣味でも、人と人の関わりや、人と周りの環境との関わりについて意識し、もっと積極的に外に出てさまざまな人と関わってみたいと思うようになりました。自分の好きなことを活かして地域づくりに参加することで、どんなことでも何かに活かせるのかもしれないと、今の自分に自信を持つことができました。
自然やまち、暮らしや観光など環境の分野はとても幅広いので、自分の興味関心を引き出し、自由な発想を持って勉強すると楽しくなってくる学科だと思います!
更新日:2015年07月02日